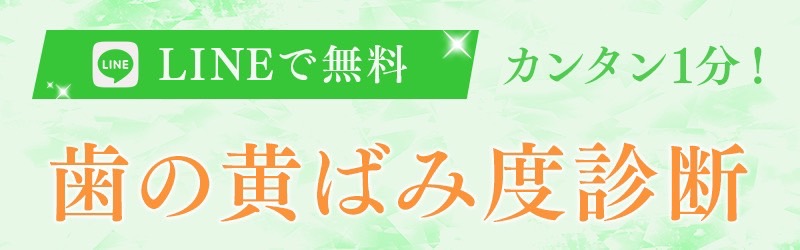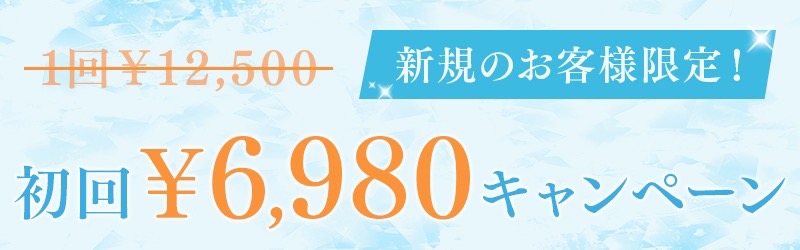歯の黄ばみは遺伝する?体質と生活習慣の影響、白い歯を守る方法

近ごろ歯の黄ばみが気になりだしたんだけど、思えば昔からずっと他の人よりも歯が黄色かった気がする…
歯の黄ばみって遺伝するの?
遺伝で黄ばんでいる場合でも白くすることはできる?
何かできる対策があれば教えてほしい!
こういった疑問にお答えします。
普段からコーヒーはあまり飲まないしタバコも吸わない、カレーやトマトなど色の濃いものも頻繁に食べるわけじゃないし歯みがきも毎食後必ずやってる…。
それなのに黄ばんでいるとなると、もともとの歯の色が黄ばんでいるとしか考えられなくなってきますよね。
でも歯の黄ばみが遺伝するなんて話、聞いたことがない人が多いのではないでしょうか。
今回の投稿では、遺伝により歯が黄ばむ可能性からその対策まで、順番にお話ししていきます!
※記事は5分で読み終わります。
歯の黄ばみは遺伝する?

結論から言いますと、歯の黄ばみは遺伝する可能性が高いです。
順番に説明していきますね。
歯はお大きく分けると3つの構造に分かれています。
外側からエナメル質、象牙質、歯髄です。
この中でも歯の色に大きく影響を与えるのが象牙質です。
象牙質はもともと黄色っぽい乳白色をしています。
象牙質の外側のエナメル質は半透明のすりガラスのような組織のため、もともと象牙質は透けて見えやすい状態になっています。
つまり、歯の色は象牙質の色によって左右されるといっても過言ではないということになります。
そしてこの象牙質は、遺伝による影響を受けやすい性質があります。
象牙質も肌や髪の毛の色と同じように、もともと白っぽかったり濃い黄色だったりと人によって色が違います。
そのため、遺伝により濃い黄色の象牙質を受け継いだ場合は、もともとの歯の色が黄ばんで見えることになります。
体質による黄ばみ

歯の黄ばみは遺伝だけでなく、その人の体質によっても影響を受けます。
そもそも日本人含め、アジア系の人はエナメル質がもともと薄い人が多い傾向にあるため、歯が黄ばんで見えやすい人が多いです。
逆に欧米人の方は歯が真っ白い方が多い印象がありませんか?
欧米人の方はもともとエナメル質が分厚くて上質な方が多いため、象牙質が透けにくく歯が真っ白く見えやすくなっています。
もちろん、日本人の方の中でももともとエナメル質が厚く上質な方もいますが、やはり遺伝が大きく関係しています。
エナメル質の厚さは歯医者さんで測ることができるので、自分のエナメル質の厚さが気になる方は歯科医師に相談してもいいでしょう。
また体質による歯の黄ばみは、エナメル質の厚さだけでなく歯そのものに影響を与えている場合もあります。
次で説明しますね。
エナメル質形成不全症
これは生まれつきエナメル質がうまく作られず、脆い状態になってしまっていることをいいます。
歯が欠けてしまっていたり、黄色や茶色などに変色していたりし、その部分の歯の歯の質はとても弱い状態になっています。
乳歯だけでなく永久歯にも見られるもので、重度の場合にはエナメル質の大半部分が形成されず、歯の表面にクレーターのようなくぼみができて凸凹することもあります。
象牙質がむき出しになる症状が見られることもあり、見た目の歯の色に影響を与えます。
また、奥歯にこの症状が見られる場合はそこから虫歯になる可能性が高く、歯が歯分進行のスピードも速くなります。
そのため、こまめに検診に行ったり、日々の歯磨きで気を付けたりと注意が必要です。
発症する原因としては、妊娠中の母親の病気やそのときに飲んでいた薬による影響、早産などが指摘されていますが、分かっていない部分が多く、決定的な原因はまだ明らかになっていません。
テトラサイクリン歯

テトラサイクリン歯は上の写真のように歯が黄色や灰色に変色してきたり、しま模様が見えてきたりしている状態になります。
これは遺伝や体質とは少し違う形で、幼少期(0歳〜12歳)のころにテトラサイクリン系の抗生物質を大量に摂取するによって起こります。
このテトラサイクリン系の抗生物質は、昭和40年代ごろにかぜ薬のシロップとして使われていました。
しかし副作用として歯の変色が起こることが確認されたため、今ではほとんど使われなくなっています。
現在では40代〜50代の人によく見られます。
なぜテトラサイクリン系の抗生物質によって歯が黄ばむのかというと、もともと黄色っぽい色をしているテトラサイクリンが歯の内側の象牙質という組織のカルシウムと結合することで沈着してしまうことによります。
そして紫外線があたることで徐々に色が濃くなっていきます。
遺伝や体質で黄ばんだ歯を白くする方法

遺伝で黄ばんだ歯を白くすることはできます。
歯を白くするとなるとホワイトニングが頭に思い浮かぶと思いますが、通常のホワイトニングでは象牙質を漂白することはできません。
先ほどもお話ししたとおり、テトラサイクリンは歯の内側の組織である象牙質の変色です。
ホワイトニングは歯の表面の汚れを落とすものになるので、象牙質の色まで白くすることはできません。
そのため、いくらホワイトニングの回数を重ねたとしても、一向に改善されないということになってしまいます。
「じゃあ一体どうしたらいいの?」という声が聞こえてきそうですが、この場合は歯医者さんでできるウォーキングブリーチという方法が効果的です。
ウォーキングブリーチ
ウォーキングブリーチとは、歯に小さい穴を開けてそこから漂白剤を注入し、歯の内側から白くするというやり方です。
この方法を使うとダイレクトに歯の内側の着色にアプローチをかけることができます。
テトラサイクリン歯以外にも、神経が死んでしまったり弱ったりしていることでも象牙質は黒色や茶色に変色してくるのですが、この場合でも効果を発揮します。
一回でキレイになる場合もありますが、回数を重ねることで徐々に白くなっていきます。
ウォーキングブリーチは歯医者さんで受けることができますが、場所によっては対応していないところもあるため、事前に確認してから行くようにしましょう。
歯みがき粉で白くすることはできる?
不可能ではありません。
歯みがき粉はフッ素が多く含まれているものを使うのがおすすめです。
フッ素には歯の再石灰化を促して歯の表面を丈夫にする効果があるため、歯の黄ばみを薄くする効果が期待できます。
フッ素によって強化された歯は、歯を溶かす酸にも強くなるため、生まれつきの黄ばみが改善されることもあります。
ただここで注意が必要なのがホワイトニング歯みがき粉です。
というのも、薬局やスーパーなどで売られているホワイトニング歯みがき粉には、研磨剤がたっぷり含まれていることが多いからです。
確かに研磨剤には汚れを効果的に落とす作用がありますが、それと同時に健康な歯まで削ってしまう可能性もあります。
それによりエナメル質が薄くなると生まれつきの黄ばみが逆に目立ってしまうことにつながります。
そして、ホワイトニング歯みがき粉はホワイトニングしたように白くなるかというとそうでもありません。
というのも、日本で売られている歯みがき粉には歯を漂白する成分を含んではならないと法律で決められているからです。
それによりホワイトニング歯みがき粉には汚れを効果的に落とす成分のみが配合されているため、あなたの歯そのものが白くなるということはありません。
こちらの記事で詳しく説明していますので、ぜひあわせてご覧ください。
ホワイトニングは歯の表面のエナメル質に沈着した汚れを漂白するのに効果的なものになるため、自分の歯の黄ばみがどこからきているものなのかを把握して、正しいアプローチをする必要があります。
もちろん、遺伝の影響があったとしても、歯の表面の汚れを落とすだけでもかなり黄ばみが改善される場合もあるので、一度試してみてもいいでしょう。
自分の歯の黄ばみが遺伝やもともとの性質によるものなのか、それとも日々の飲食や喫煙など日常的な生活の中で生まれたものなのかわからない場合は、歯医者さんで検診を受けることをおすすめします。
歯の黄ばみ以外に遺伝の影響を受けやすいもの
歯並び
歯並びは、主に顎の大きさや形、歯の大きさによって決まります。これらは親から子へ遺伝しやすいため、似た歯並びの特徴が表れることが多いです。
例えば、顎が小さいのに歯が大きい場合、歯がきれいに並ぶスペースが不足し、歯が重なって生える叢生(そうせい)が起こりやすくなります。また、顎の骨格のバランスによっては出っ歯(上顎前突)や受け口(下顎前突)といったかみ合わせの問題も生じます。
ただし、これらは幼少期からの定期検診で早期に気づければ、小児矯正によって顎の成長を利用し、将来的な歯並びの乱れを抑えることが可能です。
歯の質
歯の質とは、エナメル質の厚みや硬さ、象牙質の色や性質を指します。これらは遺伝によって左右されやすい部分です。
エナメル質が薄い場合、内部の象牙質の色が透けやすく、歯が黄色っぽく見えることがあります。また、エナメル質が弱いと酸への耐性が低くなり、虫歯が進行しやすい傾向があります。さらに、象牙質の色が濃い体質では、歯の黄ばみが強く見えることもあります。
対策としては、フッ素の活用による歯質強化や、定期的なチェックによる早期治療が効果的です。
唾液の性質
唾液は口腔内を清潔に保ち、酸を中和し、虫歯菌の活動を抑える役割を担っています。この唾液の分泌量や緩衝能(酸を中和する力)も体質によって異なり、遺伝の影響を受けやすいとされています。
唾液の分泌が少ない人は、食後に口の中が酸性に傾いた状態が長く続きやすく、虫歯や歯周病のリスクが高まる傾向があります。また、唾液が少ないと着色汚れも落ちにくく、歯の黄ばみが進みやすいこともあります。
こうした体質がある場合でも、水分摂取を意識する・キシリトールガムを噛む・口呼吸を改善するなどの習慣で唾液の働きを補い、リスクを抑えることができます。

山辺
「歯並びや虫歯のなりやすさには確かに遺伝的な影響があります。ただし、それ以上に毎日の生活習慣や親御さんのサポートが大きなカギになります。『遺伝だから仕方ない』と諦めず、予防と早めのケアを意識しましょう。
よくある質問(FAQ)

Q1 歯の黄ばみは子どもに遺伝する?
歯の黄ばみ自体が直接遺伝するわけではありませんが、歯の色調を決める要素(象牙質の色・エナメル質の厚み・透明度)は遺伝の影響を受けやすいとされています。親がもともとやや黄色味が強い歯の場合、子どもも同じような歯の色になる可能性はあります。ただし、生活習慣(食事・喫煙・歯磨き習慣など)による後天的な要因の方が大きいため、予防とケアで十分に改善可能です。
Q2 生まれつき歯が黄色っぽいのは治せる?
生まれつきの歯の黄ばみは、象牙質の色が濃い、またはエナメル質が薄いことによる体質的な特徴である場合があります。この場合、通常の歯磨きやクリーニングでは完全には白くできません。しかし、ホワイトニングで歯の色を明るくすることができます。体質による限界はあるものの、自然な範囲で歯の白さを引き出すことは可能です。
Q3 ホワイトニングは体質に関係なく効果がある?
基本的にホワイトニングは歯の表面に沈着した色素や象牙質の色を分解して明るくするため、ほとんどの方に効果があります。ただし、抗生物質(テトラサイクリン)による変色や、エナメル質形成不全などの特殊なケースでは効果に限界がある場合があります。その場合は、ラミネートベニアやセラミック治療など、別の審美的治療が検討されます。
Q4 黄ばみやすい人と白い人の違いは?
黄ばみやすいかどうかは、体質と生活習慣の両方が関係しています。体質的には、エナメル質が薄い人や象牙質の色が濃い人は黄ばみやすい傾向があります。生活習慣では、コーヒー・紅茶・赤ワイン・カレーなど着色しやすい食品や飲料を多く摂る人、喫煙者、歯磨きが不十分な人は黄ばみやすい傾向にあります。逆に、ステインをつきにくくする生活習慣+定期的なクリーニング+ホワイトニングを取り入れることで白さを保ちやすくなります。
まとめ
歯の黄ばみは遺伝しますし、体質によっても黄ばむことがあります。
しかしアプローチの仕方によっては改善されることもあります。
大切なのはあなたの歯の黄ばみがどこからきているものなのかを把握し、正しいアプローチをすることです。
遺伝や体質によるものなのか、日々の飲食や喫煙などの生活習慣の中から生まれたものなのか、原因がよく分からない方はまずは歯医者さんでの検診をおすすめします。
原因を知り、自分にあった方法を試していくようにしましょう!

石川県歯科衛生士専門学校 卒業
フリーランスの歯科衛生士として、ホワイトニングサロンオーナーとして独立。
また歯科衛生士の新しい働き方として、個人のSNSを起点に、キャリアアップを目指す歯科衛生士さんの応援やサポートをしている。
2022年2月〜Kiratt広報としてオーラルケア知識などのYoutube配信と広報活動。
2022年5月〜Kiratt 金沢鞍月店にて独立。